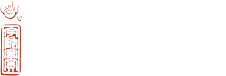日本の伝統「かまど」
火と向き合えるのは人間という種族だけ。
大変有難いものですが、横着をすると危ないものにもなります。
畏敬の念を持って、火と向き合わなければいけないのです。
ぼーっとあたたかい火を見るとリラックスできる、
という声が聞こえてきます。
生火には特別な存在・感覚があるのです。
エアコンではなく、薪ストーブのあたたかさに惹かれる。
炊飯器ではなく、かまど炊きのお米の美味しさに惹かれる。
あなたも、「本能的に惹かれる美しさ」を感じませんか?
かまどとは

昔は、かまどで直火を用いて調理をしていました。
1950年代まで、どこの家庭でも当たり前に存在していた調理設備です。
しかし、電気炊飯ジャーの登場とともに台所の姿も激変し、
かまどは次第に姿を消していきました。
現在の日本では、かまどを見ることさえ少なくなったのです。

かまどが存在する環境でも実際に使用されることは少なく、
眠った状態のかまどがたくさんあります。
しかし、「かまど炊きのお米が食べたい」という思いが
日本人の心の底にあるのではないでしょうか?
かまどの存在価値を知り、見直していただきたい。
わたしたちは「かまど」にこだわり、
かまどで炊いた本当に美味しいお米を食べていただきたいのです。
宇陀かまど
誕生
昔ながらの 「羽釜ご飯」 が美味しい事は
お米を主食としてきた日本人なら誰もが周知の事実です。
しかし、実際に一般の家庭環境でかまどを使い
羽釜のご飯を戴く事はなかなか難しくハードルの高い物でした。
屋内使用可能な固形燃料を用いても簡単に扱え、
卓上で炊きたての美味しい羽釜ご飯を食する事が出来たら…
そんな想いのもと、本格かまどの施工経験をフィードバックし、
伝統的左官技術を駆使して「宇陀かまど」は生まれました。
宇陀かまどについて
固形燃料を用いマンションなど現代住宅でも使用可能な卓上型かまどです。
全国の左官職人が様々な卓上かまどを製作していますが、「宇陀かまど」は特許庁に意匠登録された当方のオリジナル品です。
荒神竈
荒神竈について
家の中心的存在の竈。
なかでも「火の神様・家神様」が降臨する場所として
祭壇的役割を担う特別な竈の事を「荒神竈」と呼び、
人々は火への感謝・日々の暮らしの安全を願いました。
〜八百万の神の国・日本〜
大切にしたい祈りのカタチです。