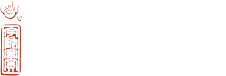宇陀松山は宇陀山地に位置し、
城下町から商家町として発展した町並みには
前川と呼ばれる水路が走り、
せせらぎの音とともに独特の景観をつくりだしています。
宇陀松山の伝統的景観を構成する要素として、
町家・洋館・神社建築・土蔵・石碑・門・堀などがあり、
これが広範囲にわたって分布しています。
松山地区は南北に伸びる二本の通りと、
それをつなぐ東西の通りで構成されています。

緩やかなカーブを描いて伸びる道では、家の妻が見え、
背後に見える山々と調和した景観を楽しむことができます。
このように宇陀松山は
各時代の歴史と文化が重層的に堆積しており、
きわめて貴重な文化遺産を継承している町なのです。
宇陀松山観光案内はこちら
昔ながらの伝統の作り

屋根瓦の種類
松山地区の町家は、桟瓦葺の家が大部分を占めています。軒先に置かれている瓦(軒瓦)には「まんじゅう」「鎌」「一文字」があります。鎌には模様のないものと唐草文などの模様がついたものがあります。建物によっては庇と大屋根で異なる軒瓦を使用しているものや、庇の途中から軒瓦の種類が変わるものがあります。屋根の頂上に載る棟瓦にも、いくつもの種類があります。
また、棟の端に載っている瓦(鬼瓦)には、家紋や縁起物等が刻まれています。

座敷玄関
間口の大きな家には座敷玄関があります。
冠婚葬祭などの特別なときに使う出入り口で、直接座敷に行けるようになっています。座敷玄関を持つ家では、普段の出入り口ではなく座敷玄関の方を「ゲンカン」と呼ぶようです。

袖うだつ(袖壁)
家紋入り模様
町家の中には、袖うだつと呼ばれる袖壁があります。模様や家紋を入れているものが多いですが、
中には独特の形を持ったものもあります。

変形の虫籠窓・格子状の虫籠
2階の窓は虫籠窓(むしこまど)を持つものと、木製建具の窓を持つものとがあります。松山地区では、多種多様な虫籠窓を見ることができます。

漆喰壁 大壁・漆喰壁 大壁
漆喰の大壁がある2階には、虫籠窓が設けられています。
※資料宇陀市教育委員会松山地区まちづくりセンター
宇陀松山地区内で見つけた
先人の知恵

木製の建具
老朽化のため解体された建物の跡地に残っていた、
廃棄処分の建具(雨戸)の戸車を見てびっくり。
銭形平次でおなじみのお金「寛永通宝」を数枚重ね合わせ、
中心の四角い穴を円形に加工。
古い建物は先人の知恵が詰まっていると感じました。

左官職人の絵心
土蔵の窓の上に雨よけの庇がついていますが、
その屋根を支える袖(持ち送り)に模様が描かれているのをよく見かけます。
その工事に携わった職人の技術力、遊び心がよく表れている部分です。
しかし漆喰に描かれているものは改修工事など
塗り替え時に消失してしまう運命にあります。
各地に残る特殊な“鏝絵”“伊豆の長八”の作品のように芸術品と評価される
大掛かりな物なら保存される可能性もありますが、
大半は人目につかないうちに消えて行くのが常です。

陀松山地区の江戸時代創業 老舗の造酒屋の土蔵改修
工事で創建当時の職人の遊び心の名残を発見しました。
“唐草”など伝統的デザインが多いのですが、
縁起が良いとされる白兎が一筆書きのように生き生きと
描かれていたのです。
塗り替え工事なので当然削ぎ落とすことになったのですが、
その前にカメラに収めました。